

「鮭の日」を祝う!サーモン寿司誕生40周年の魅力とは
食欲の秋!11月11日を鮭の日と称して祝おう
11月11日という日の多彩な記念日。中でも「鮭の日」として知られるこの日は、食欲の秋を感じられる特別な日です。一般社団法人日本記念日協会によって認定され、食に関連する様々な記念日が揃っている11月11日ですが、鮭の日が設けられた理由はその形状に由来します。実際、「鮭」の「圭」という漢字の成り立ちが「十一」の組み合わせとなっていることからこの日が選ばれたのです。
この日は食欲をそそる季節であり、秋の味覚が豊富に登場します。米、サツマイモ、栗、キノコ、旬の魚である秋刀魚、鮭が特に人気を集めるといわれています。そこで、今回は鮭の日に絡めて、特に回転寿司で愛され続けているサーモンの魅力を掘り下げてみたいと思います。
サーモンの地位を確立した回転寿司
サーモンはまさに回転寿司界のアイドル的存在です。毎年実施されるマルハニチロの消費者調査では、サーモンが14年連続で人気ナンバーワンに偉業を達成しています。また、くら寿司のランキングでもサーモンは常に上位に位置し、「あぶりチーズサーモン」も多くの支持を得ています。これは、1980年代にノルウェーから生鮮サーモンが輸入され、回転寿司で提供されることをきっかけに、日本中にその美味しさが広まったからです。
魅力溢れるサーモンの歴史
サーモンは長い歴史を持っています。1980年代、日本にノルウェーからの養殖サーモンが伝わり、生食文化が形成されました。その当時まで、鮭は火を通して食べるものであり、生で食べることは一般的ではありませんでした。しかし、回転寿司の登場により、サーモン寿司が販売されると、その美味しさにみんなが虜に。サラダやカルパッチョなど、幅広い料理に使える点も人気の要因です。この時期から、サーモンは年齢や性別を問わず多くの人々に支持されることになりました。
現在、日本のサーモン消費量の約85%はノルウェーからの輸入に依存していますが、国内でもサーモン養殖が進展しています。特に三陸や瀬戸内海、九州沿岸での海面養殖など、新しい取り組みが目立つようになっています。日本の気候に影響されながらも、養殖技術は進化し、夏場には高温になる海水を避けたり、人工環境での陸上養殖が注目されています。
地域に根差した新たなサーモンブランド
最近では、地域の特性を活かした「ご当地サーモン」が誕生し、新たな名物として注目を集めています。例えば、青森県の「海峡サーモン」は外海で育てられる珍しい国産サーモンで、兵庫県の「神戸元気サーモン」は酒粕をエサに用いることで知られています。ほかにも、栃木の「うつのみやストロベリーサーモン」や、広島の「広島レモンサーモン」といったユニークな商品も存在します。これらの養殖産業は、地域に雇用や経済効果をもたらす存在として、今後の発展が期待されます。
ノルウェーサーモンとの関係
ノルウェーと日本の関係も深く、2025年は日本とノルウェーの外交関係樹立120周年、ノルウェーのサーモンが日本に上陸してから40周年という記念すべき年です。この機会に、ノルウェー大使館の水産参事官ヨハン・クアルハイム氏にインタビューを行い、サーモン文化の形成に対する冬の味覚の重要性、ノルウェーの供給体制などについて伺いました。
クアルハイム氏は、「サーモンは日本の食文化に欠かせない存在であることは非常に嬉しい」と述べ、生食文化の普及や回転寿司での展開がいかに貢献してきたかを強調しました。
まとめ
このように、11月11日の「鮭の日」は、美味しいサーモンを心ゆくまで楽しむ良い機会です。サーモンの魅力には、地元の新鮮さはもちろん、国際的な交流や養殖技術の進化も含まれ、今後の日本の食文化の発展にも大いに貢献していくことでしょう。これを機に、鮭の日を祝うと共に、サーモンの多様な魅力をぜひ体験してみたいものです。










トピックス(グルメ)





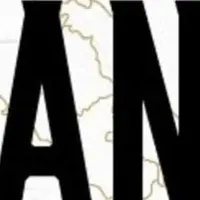




【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。