

島根の小学生に伝える海の恵みと寿司の未来に向けたSDGs授業
権利を学ぶ出張授業「お寿司で学ぶSDGs」
来たる2025年11月13日、一般社団法人海と日本プロジェクトinしまねと、くら寿司株式会社の共催による特別な授業が宍道小学校で行われる予定です。この出張授業は、「お寿司で学ぶSDGs」をテーマにしており、次世代を担う子どもたちに海洋環境や漁業、そして持続可能な食の在り方について深く考える機会を提供します。
この取り組みは、夏に隠岐諸島で行われた「隠岐めしと歴史探険隊」の体験学習に基づくもので、参加した児童たちが学んだ漁業の現状や海の恵みの大切さを伝える動画が上映されます。授業は、子どもたちが「海の恵みを未来につなぐ」方法を考えるきっかけとなることを目指しています。
漁業資源の現況と滋味深い授業内容
現代の日本では、漁業資源の減少や、食品ロスといった問題が深刻化しています。このため、今回の授業では特に「SDGs」の目標を意識し、子どもたちの主体的な学びを促進する内容となっています。具体的には、「お寿司屋さん体験ゲーム」や「魚模型を用いた海の現状解説」、さらには「課題解決ワークショップ」を通じて、児童たちは自身の行動が海に与える影響を学びます。
授業の冒頭では、隠岐諸島での体験学習の内容を振り返り、その中での海産物の歴史や漁業の現状を紹介します。地元の漁師からの教えを通じて得た知識を、映像を通じてより広い視野で理解してもらいます。
それぞれのセッションの魅力
授業は、3つのセッションに分かれて構成されており、それぞれのセッションが子どもたちに具体的な体験を提供しています。最初のセッションでは、「未来ではお寿司が食べられなくなる!?」をテーマに、現在の漁業が抱える問題や、様々な環境問題を取り上げます。映像と模型を用いて、分かりやすく理解を促進します。
次に続くセッションでは、「お寿司屋さん体験」として、来店客の注文に応じて寿司を提供するゲームに挑戦します。このゲームを通じて、過剰提供や廃棄の問題を感じ、食品ロス削減の重要性を身をもって体感します。
最後のセッションでは、各グループで「どうすればお寿司を未来にも食べ続けられるか」を考え、様々な解決策を発表します。このプロセスを通じて、一人ひとりの創意工夫が持続可能な社会に向けたアクションにつながることを期待しています。
地元の食文化と未来への架け橋
さらに、この授業は松江市内の他の小学校でも行われる予定で、次世代への教育的な取り組みが地域全体に広がります。松江の子どもたちが地元の海の恵みを学び、その大切さを再認識することで、彼らの将来にわたって「美しい海」を守る意識が育まれることを願っています。
興味がある方は、11月13日の授業を実際に取材してみてはいかがでしょうか?授業を通じて公式の取材が行われる店舗では、採用されるメニューや食品ロス削減に取り組む姿勢を知る良い機会となるでしょう。
今回の授業を通じて、子どもたちが海の重要性や持続可能な社会を築くための理解を深め、自立した行動を取る力を育むことを心から期待しています。



関連リンク
サードペディア百科事典: SDGs くら寿司 海と日本プロジェクト
トピックス(イベント)






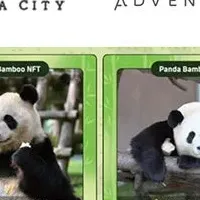



【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。