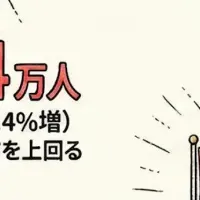
紀伊山地の霊場と参詣道の歴史的意義と未来への継承
紀伊山地の霊場と参詣道の重要性
紀伊山地の霊場とその参詣道が、2023年で世界遺産登録から20年を迎えました。この記念すべき年に、地方自治体や様々な団体がイベントを開催し、地域の魅力を再発見しようとしています。
世界遺産としての登録は、単なる観光資源の認知度を高めるだけでなく、私たちが持つ文化遺産や精神的財産を深く掘り下げるきっかけともなっています。特に、紀伊山地における信仰の形態は、真言密教や修験道、さらには神道といった多様な宗教観が融合しています。このような「神仏習合」の考え方は、紀伊山地独自の精神性を育んできました。
紀伊山地に根付く神仏習合の思想
高野山の真言密教、吉野大峯の修験道、そして熊野三山の神道信仰は、いずれも深く結びついています。特に注目したいのは、高野山周辺に存在する丹生都比売神社や熊野那智大社など、霊場同士が互いに影響を与え合いながらその歴史を刻んできた点です。この背景には、神仏の精神を受け入れ、共存させる柔軟な考え方が根底にあります。
このような思想は、西洋文化の一神教的な視点に対し、私たち日本人が持つ「和」の心を強調しているともいえます。「あれか、これか」だけではなく、「あれも、これも」と受け入れる寛容な精神が、多くの人々を引き寄せる要因になっています。
熊野の魅力と女性の受け入れ
古来、聖地は女人禁制が一般的でしたが、熊野は女性たちにとっても参詣の場でした。和泉式部が月の障りのために赴けないとき、夢の中で熊野権現が現れ、その道を歩むことを助けたという伝説も、その例です。これにより、熊野は「ジェンダー平等の元祖」としての役割も果たしています。
。
さらに、『小栗判官照手姫』の物語では、歩けない餓鬼阿弥としての姿となった小栗が、土車で熊野を訪れ、再び若武者に戻る様子が描かれています。ここでの「よみがえり」は、熊野が人生の逆境を乗り越える象徴でもあるのです。こうした物語は、観光だけでなく、精神的な旅としても、多くの人々を魅了しています。
未来への受け継ぎ
紀伊山地の霊場と参詣道は、和歌山の独特な文化的財産であり、県民としての誇りでもあります。私たちはこの貴重な遺産を次世代に引き継ぎ、育んでいく責任を持っています。地域の人々と共にイベントを開催し、その文化や価値を再確認することが重要です。これからの未来に向けて、紀伊山地の精神性や神聖な風景をしっかりと守り、次の世代に受け継いでいきたいものです。
紀伊山地に根ざした信仰と文化は、私たちが思っている以上に深いものであり、一度足を運ぶことでその真髄をより理解できることでしょう。地域とのつながりを深め、この素晴らしい遺産を楽しむ機会を大切にしていきましょう。
トピックス(旅行)
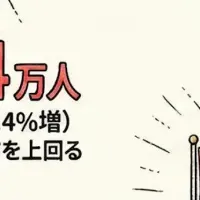

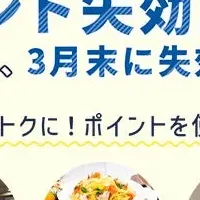
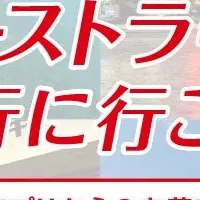
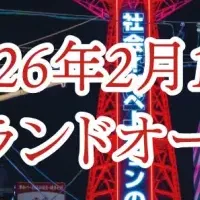


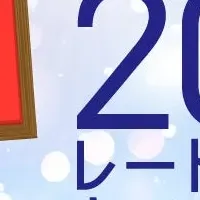
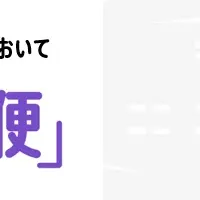

【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。